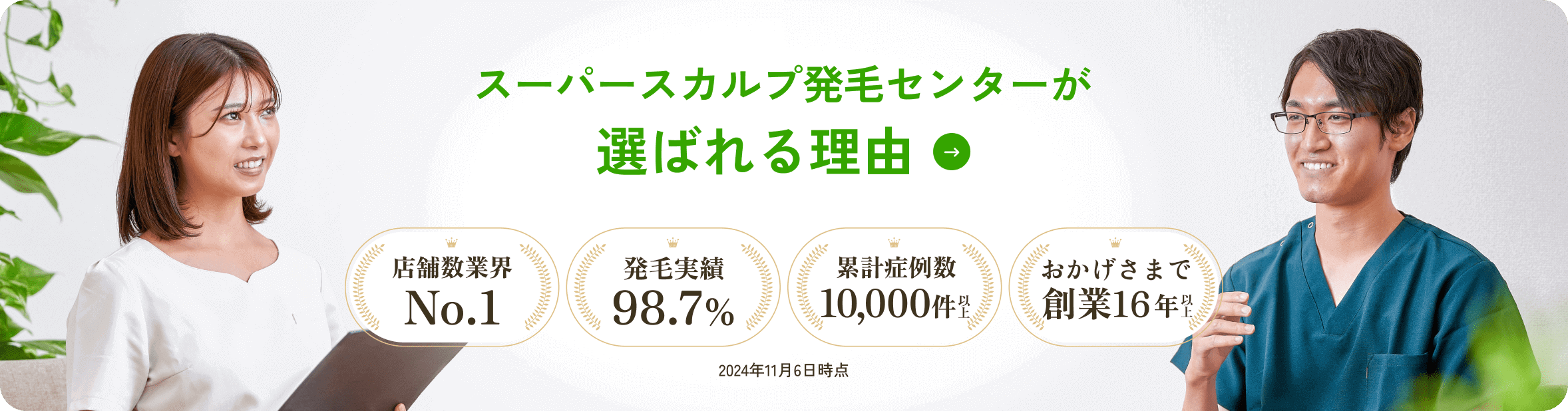髪の毛は生えます!正しい知識で発毛に
発毛・育毛コラム一覧
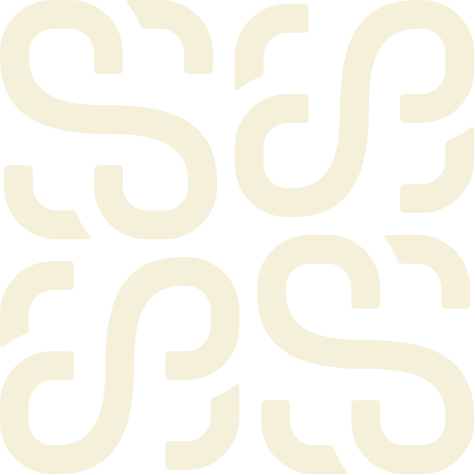
category
-
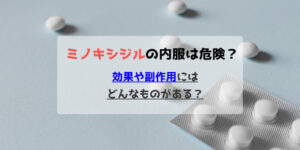
食事・生活習慣etc
2023.03.13
ミノキシジルの内服は危険?効果や副作用にはどんなものがある?
-
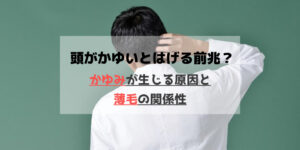
薄毛・抜け毛の原因
2023.03.09
頭かゆいとはげる前兆?かゆみが生じる原因と薄毛との関係性
-
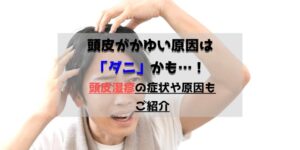
薄毛・抜け毛の原因
2023.02.18
頭皮がかゆい理由はダニが原因かも?頭皮湿疹の症状や原因・予防方法
-
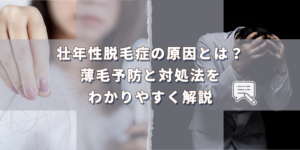
2023.02.09
壮年性脱毛症の原因とは?薄毛予防と対処法をわかりやすく解説
-

薄毛・抜け毛の原因
2023.01.27
マカ・亜鉛の効果とは?男性にも女性にも嬉しいメリットがいっぱい!
-

頭皮と髪の正しいケア
2023.01.27
イソフラボンは男性の薄毛予防に効果的?イソフラボンが多い食品は?
-
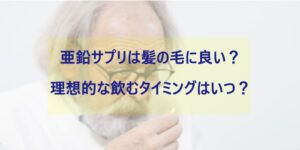
2023.01.24
亜鉛サプリは髪の毛に良い?理想的な飲むタイミングはいつ?
-
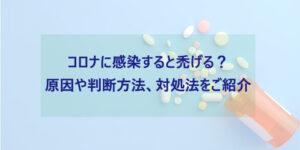
頭皮と髪の正しいケア
2023.01.24
ザガーロの成分デュタステリドの効果は?副作用などの注意点も解説
-

頭皮と髪の正しいケア
2023.01.18
シャンプーを使わない「湯シャン」の効果とは?正しいやり方も解説
-
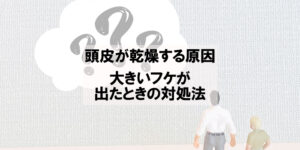
頭皮と髪の正しいケア
2022.12.23
頭皮が乾燥する原因とは?大きいフケが出たときの対処法をチェック
-

薄毛・抜け毛の原因
2022.12.15
悪玉男性ホルモンが増える原因は?ジヒドロテストステロンの抑制方法
-

薄毛・抜け毛の原因
2022.11.15
男性ホルモンを減らす方法はある?薄毛との関係性や身体への影響
-

頭皮と髪の正しいケア
2022.11.08
つむじが痛い原因とは?つむじの痛みの対処法や予防方法をご紹介
-
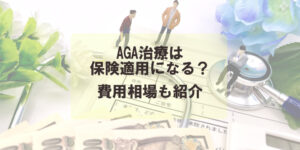
発毛実績と詳細
2022.10.07
AGA治療は保険適用になる?治療にかかる費用相場はどれくらい?
-
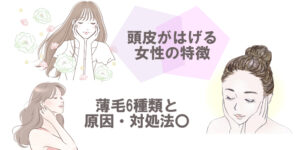
薄毛・抜け毛の原因
2022.10.05
頭頂部がはげる女性の特徴とは?原因とあわせて対処法もご紹介
-
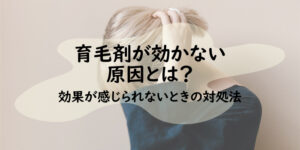
発毛実績と詳細
2022.09.15
育毛剤が効かない原因とは?効果が感じられないときの対処法
-
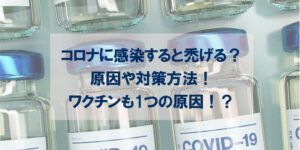
薄毛・抜け毛の原因
2022.09.07
コロナに感染すると禿げる?原因や判断方法、対処法をご紹介
-
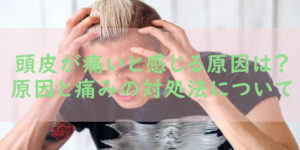
頭皮と髪の正しいケア
2022.08.30
頭皮が痛いと感じる原因は?痛みの対処法についてご紹介します
-
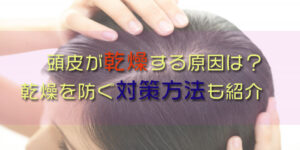
頭皮と髪の正しいケア
2022.08.26
頭皮の乾燥はかゆみやフケに繋がる?頭皮乾燥の原因や対策方法を紹介
-

頭皮と髪の正しいケア
2022.08.25
フケが増える原因は乾燥や洗い残し?フケを減らす改善・予防方法とは